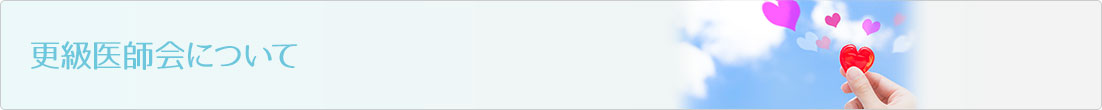雌のカブトムシ
2020/2/5
久しぶりにきっぱりとした夏の日。
長い梅雨がようやく明けて初めての土日、クリニックは二連休だ。
普段は屋内ばかりに居るので、夏の日射しは眩しすぎるくらいに明るい。
頭上から容赦なく照りつける盛夏の太陽は、木々の葉の一つ一つまでくっきりとしたシルエットを地面に投影して、夏模様を描画していく。
柏崎で親類の法要に参列後、海岸からほど遠からぬ寺院へ墓参に来た。
街並みから隔離された墓地の木立は昆虫たちの天国で、蝉時雨が僧侶の読経を伴奏に変えた。
線香を上げる間も、キアゲハ、そして次はカラスアゲハと、広いストライドで駆け抜けるアスリートのように、蝶が優雅に舞っていく。
少年の頃から無類の昆虫好きだった私には、何と心地よい情景だろう。
私の目の前のランウェイを、それぞれの個性を主張して通り過ぎていく昆虫たちを見ていたら、子供だった頃の夏へのノスタルジアのドアが開いた。
少年時代の私はカブトムシとクワガタにほとんどの夏を捧げたと言っても過言ではない。
夏休みには実家に程近い頼朝山へ毎日昆虫採集に出かけた。
頼朝山は、豊富な甲虫類を授かることができる、私にとっては聖なる山であった。
毎日1回、時には2回出かけたので、虫が居る木は隅から隅まで知り尽くしていた。
採った虫たちは飼育箱でだいじに飼って、暇さえあればその生態を眺めて満足していたものだ。
カブトムシと言えば、母が亡くなった夜、不思議なことが起こった。
葬儀の段取りなどで疲れ果てた私は、深夜夕食を求めて近所のコンビニに立ち寄った。
買い物を済ませて出ようとしたとき、入り口のマットの上に仰向けでもがいているカブトムシを見つけた。
手に取ると立派な雌のカブトムシであった。コンビニの灯りに吸い寄せられて飛来したのだろう。
その瞬間、これは母だと直感した。
母は私が少年時代夢中だったカブトムシに姿を変えて現れたのだと。
脳卒中で体が不自由だった母は、療養を兼ねて神戸の姉の家に行き、そこで病態が悪化して長野に戻ることができなくなり、遠く故郷を離れて永眠した。そんな母の魂はさぞかし帰郷したかっただろうと想像できる。
私はそのカブトムシを取り上げて服の胸にとまらせた。
そして、抱きかかえるようにして家まで連れて帰った。
不思議にカブトムシは私の胸元から逃げようともせずしっかりしがみついたままだった。
小一時間カブトムシはカーテンの上でじっとしていたが、就床直前に庭の沙羅の木にとまらせてあげた。
翌朝確かめると、カブトムシの姿は既にいなくなっていた。
沙羅双樹は、お釈迦様が入滅した場所に生えていたとされる木である。
母の魂も無事に旅立ったのかもしれない。
その時以来昆虫は亡くなった人の化身という私の思い込みが定着した。
モンシロチョウを見れば自分をこよなく愛してくれた祖父だと思い込み、キアゲハを見れば叔母だと感じた。
母がカブトムシに化身したのは一度きりで、その後はカラスアゲハやクロアゲハとなってことある毎によく現れた。
頻繁には現れないけれど風に乗ってふいに訪れるオニヤンマやギンヤンマは父だと思う。
こうして私は昆虫を見ては故人を想う。
故人の様々なエピソードやシーンをニューロンのネットワーク、つまりセル・アセンブリ(細胞集成体)をフル稼働して再生する。何度も何度も。
しかし、このセル・アセンブリも私の脳の活動が健康である前提のもとでしか存在し得ない。
開業して6年、初診時は軽度認知障害もしくは軽い認知症だった患者さんたちの海馬は月日と共に菲薄化し、大切なセル・アセンブリが無情にも確実に奪われていく。その様を日々観察していると、やるせない想いが私を満たす。
かけがえのない大切なニューロンの活動を何とか健康に保つすべはないものかと、歯がゆい思いと憤怒に似た感情が日々私にジャブを繰り出してくる。
そもそも人の生涯は一度きりしか上映されない映画のようなものだから、観た者がきちんと脳裏で再生して、そして何らかの形で記録に残すことが、その人がどのように生きたかの証となる。
自分の大切な人のことはこうして随筆などの文章にして、そして患者さんのことは診療録の中に、せっせと労を惜しまず記録していかなければならないと痛感する。
お盆もすぎ、あのうだるような暑さはあっさりと去った。
今日は母の月命日だ。ふと窓外を黒い影がよぎったので窓に近づいてみると、見事なカラスアゲハが楽しげに庭を舞っていた。間違いなく母だろう。
私にとっての昆虫は、いまは亡き大切な人々を回想するための使者なのかもしれない。